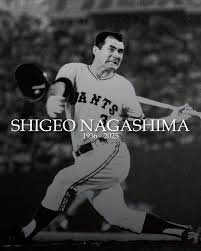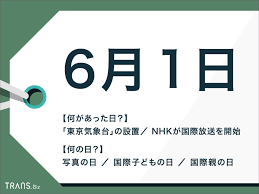ブログ - 2025年6月
日経平均4万円台
日本株の上昇に弾みがついてきました。27日の東京株式市場で日経平均株価は大台の4万円台を5ヶ月ぶりに回復しました。企業による資本効率の改善のほか、M&Aを通じて成長を目指す企業が増え始めています。日本株を再評価する海外投資家の買いが相場を押し上げています。世界株の最高値更新など市場の雰囲気は好転していますが、肝心要!日本株のさらなる上昇には、個々の企業の稼ぐ力を高めることが不可欠です。
「健康中国2030」
世界一の消化器がん大国と言われる中国は、国家戦略「健康中国2030」を掲げ、医療水準の向上を図ります。健康診断でのがん発見率や手術のレベルは依然として低く、日本企業で診断や手術の訓練を受ける医師も多くいます。高齢化が進むなかで健康寿命を延ばそうと、日本に学びながらがんの早期発見・治療を目指しています。日本(企業)は、医療分野を含めさまざまな形で中国の経済発展や生活向上に貢献しています。こうした取り組みをもっと多くの人が知れば日中友好にも寄与するのだと思います。
M&Aに新たな資格
中小企業庁は中小企業のM&A(合併・買収)を手掛けるアドバイザー資格を2026年度にも創設します。仲介者に財務や法務の知識と実務能力を求めます。中小のM&Aでは悪質な仲介を繰り返す事業者もいます。事業承継の需要が高まるなか、売買時のトラブルを防ぎ、市場の活性化を促すのが目的です。資格の取得試験ではM&Aの進め方や財務、税務、法務などの知識を問うことを想定しています。仲介時に必要な倫理規定の遵守も求めます。制度運営は民間に委託する方針です。
「高卒採用バンク」
『1人1社の就職先を学校が決める』高校生の就活に根強く残るこの慣習に挑むのが高卒採用バンクです。浜松市出身の遠藤隼聖社長(22歳)が学生時代に起業しました。高校生が自ら企業を調べ、比較検討できる高卒就活プラットフォーム「みらいショップ」を立ち上げました。中小企業の人材獲得を支援し、学校の進路指導も後押しする形です。いつの時代も、慣習、偏見、既成・固定概念を打ち破るのは若者です。それを応援するのが年配者でもあります。(大手人材企業は制度上の制約や採算性の低さから高卒市場に本格参入していない➡AI技術の進展で専門性の低いホワイトカラーなどの需要が減り、高齢化により経済的余裕も少なくなり、高卒就職率が伸びる可能性がある)
AIで人員を半減
アフラック生命保険は人工知能(AI)を使ってコールセンターの人員数を半減します。オープンAIと組んで顧客に自動で応答するシステムを開発しました。500億円のコスト減を見込んでいます。保険会社は顧客対応や営業で多数の人手がかかります。AIが従業員に置き換わる段階まで進み、労働集約型だった保険業の事業構造を変える可能性があります。コールセンター女性社員と顧客とのやり取りのTVCMも様変わりする日も近いですね。
交通反則切符(自転車)
自転車の交通違反に関する交通反則切符(青切符)が2026年4月1日から導入されることが正式に決まりました。対象となるのは16歳以上で、113の違反行為について3,000~1万2,000円の反則金を定めています。反則金は2人乗りや2台以上の並走が3,000円などとしています。車両運転者や歩行者にはよいですが、気軽に自転車にも乗れなくなります。
「コメ作況指数」廃止
小泉進次郎農相は16日、コメのとれ具合を示す「作況指数」を今秋から廃止することを表明しました。過去30年の傾向をもとに判断する手法が冷害の減少など気候変動によって「生産現場の実態と合わなくなってきた」と説明しています。今後は生産量を把握するため人工衛星のデータを活用するなど収穫量調査の精度を高めます。今まで生産量さえ正確に把握できなかったことを考えると、需要と供給のバランスなど対策がしっかりとれなかったのは当たり前ですね⁉
「加熱寿司」
妊婦向けに開発された「加熱寿司」がSNSなどで反響を呼んでいます。発案したのは、元日清食品社員の渡辺愛さん(34歳)です。きっかけは自身の妊娠です。「生ものは控えてくださいね」という医師の一言に発奮しました。出産後に独立し商品化すると意外なニーズがあることが分かったということです。このケースも「不=課題」解決の結果です。
「1人2万円給付」首相表明
石破首相は13日、物価高対策として夏の参院選の自民党の公約に国民1人あたり2万円の給付を盛り込むことを表明しました。子どもと住民非課税世帯の大人には1人2万円を加算します。首相は「物価高対応は賃上げが基本だが、物価上昇を上回るまでの対応も必要だ」としています。財源は税制動向をなどを見極めながら適切に確保し、赤字国債に依存しないとしています。現金収入は有り難いと思う反面、どうみても参院選を見据えた付け焼刃対策と思えてなりませんが・・
「仮装身分捜査」
警視庁は9日、警察官が身分を偽り犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」を通じ容疑者を逮捕したと発表しました。仮装身分捜査による摘発は全国で初となります。犯罪の予兆を察知し、着手前に実行役の身柄を確保したとみられます。ドラマのような「おとり捜査」みたいなものでしょうか⁉恣意的な運用になっていないか、事後的に検証・チェックする仕組みも必要だと思います。
建設業の停滞(人手不足)
国内で商業施設や工場などの建設が停滞しています。建設会社が手元に抱える工事は金額にして15兆円を超え、過去最大に膨らんでいます。かねてより深刻な人手不足に2024年からの残業規制が拍車をかけています。働き手の確保が難しいのなら、デジタル化によって生産性を高めるなければ、民間企業の設備投資や公共投資の制約となり(工場の建設が停滞すれば、備え付ける機械の投資の遅れにも波及する)、日本の成長力が一段と下振れする恐れがあります。
家庭用精米機需要増
スーパーなどで新米の品不足が続くなか、玄米を白米にする精米機や冷蔵保存用の保冷庫の需要が急増しています。家庭用精米機大手のツインバードは2025年度の販売計画を当初の2.5倍に引き上げました。保冷庫大手も5月の販売が前年同月の2倍を超えました。各社は「家庭内備蓄が増えた」「一度にまとまった量を販売するなど農家の売り方が変わった」と消費行動や流通の変化を指摘しています。“顧客ニーズあるとことに販売チャンスあり”です!!
日本郵便の運送事業許可を取消処分へ
国土交通省は月内にも日本郵便の自動車貨物運送の事業許可を取り消す方針です。全国の郵便局で配達員への法定点呼が適切に行われていなかったことが最大の要因です。同社のトラックなど約2500台が5年間使えなくなり、郵便物や荷物の輸送に影響します。郵便・物流事業の継続には委託拡大が必要で、収益の下押し要因となります。当たり前のことが守られていない企業は、市場から退場するほかありません。
食文化にも人間国宝を認定
文化庁は重要無形文化財の制度を約50年ぶりに見直し、料理人や杜氏といった食文化に関わる人を人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定できるようにします。芸能と工芸技術に限られている対象分野に、食などの生活文化を追加します。優れた技術を保護して後世につなげるのが目的です。さて、栄誉ある食文化に携わる最初の人間国宝はだれになるのか⁉発表が待たれます。